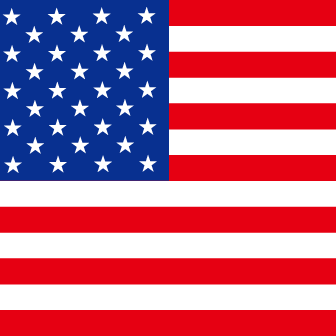よくある質問
【基本情報】
Q1 御朱印はいつ受けられますか?
A
〇夏時間(3月~10月):8時~17時
〇冬時間(11月~2月):8時~16時
〇昼休み(通年):12時~12時30分
〇定休日なし
※年中無休の為、時間内であれば毎日御朱印が受けられます。
御朱印料は500円をいただいております(重ね印:2巡目以降は200円)。
駐車場料金や入山料(入場料)はいただいておりません。
Q2.地図やモデルコースが欲しいです
A
資料請求のページ☜からお申込みいただけます。
無料でお送りいたします。
Q3.巡礼用品が欲しいです
A
秩父札所の公式巡礼用品通販のページ☜からお求めいただけます。
納経帳(御朱印帳)・経本・納札・おいずる(白衣)などは公式用品があります。
現地の各札所にも用意があり、特に1番四萬部寺・13番慈眼寺に種類が豊富です。
秩父札所の公式掛け軸は、現在取扱いがございません。
掛け軸につきましては、札所1番または札所13番慈眼寺までお問合せください。
札所1番 :0494-22-4525
札所13番:0494-23-6813
Q4.秩父札所の一覧を見たいです
秩父札所のパンフレット☜をご覧ください
Q5.34ヶ所すべてを巡礼するには何日かかりますか?
A
秩父札所の一巡は約100kmです。
車(自家用車)では3~4日
徒歩(電車/バス)は7~8日
詳しくは秩父札所巡礼モデルコース☜をご参考ください。
連続した日程ではなく、月に1回・年に1回など数回に分けて巡礼しても構いません。
移動手段について
徒歩だけが巡礼ではなく、車やバイク・自転車などでの巡礼も立派な札所巡りです。
全ての札所寺院には駐車場があり、駐車場料金は一切いただいておりません。
Q6.お寺の呼び方を教えてください
A
秩父札所の寺院は、それぞれ番号で呼ばれることが多いです。
例えば、秩父札所1番四萬部寺を「1番」または「1番さん」と呼びます。
道中で道を尋ねる時は、「久昌寺はどちらですか?」ではわからない場合が多いので、
「25番はどちらですか?」と番号で尋ねてください。
Q7.参拝の作法を教えてください
A
「合掌一礼」が寺院における基本の作法になります。
「合掌一礼」とは、手を合わせる「合掌」をしたまま、お辞儀(低頭)する「一礼」を行う動作です。
山門や観音堂で合掌一礼をして、楽しく巡礼をしていただけると幸いです。
詳しくは「参拝の心得」☜をご覧ください。
【巡礼するにあたって】
Q1.納経(御朱印)を受けるにはどうしたら良いですか?
A
納経帳(御朱印帳)をお持ちください。
参拝の証として、各寺院の御朱印をいただくことができます。
秩父札所専用の納経帳は、こちらの公式巡礼用品通販のページ☜からお求めいただけます。
また現地の各札所にも公式納経帳の用意があります。
※お好きなデザインの御朱印帳をご持参いただいた場合でも、御朱印を受けられます
Q2.準備する物に決まりはありますか?
A
決まりはありません。
巡礼・参拝するだけであれば身一つで問題ありません。
歩きの場合は、杖の使用を用意してもいいかもしれません。
始めは納経帳(御朱印)だけでも問題ありません。
慣れてきたり、より本格的に巡礼する場合は下記(①~②)もご準備ください。
①経本 ②納札
Q3.服装に決まりはありますか?
A
決まりはありません。
ハイキングなどの歩きやすい服装と靴をオススメします。
歩きの場合は、杖(トレッキングポールなど)の使用もオススメします。
秩父札所巡りに正装といったものはありません。
本格的な装束は「巡礼の晴れ着」と呼ばれています。
①おいずる(白衣) ②菅笠 ③金剛杖 ④輪袈裟 ⑤持鈴
などをご準備ください。
Q4.秩父の道路状況を知りたい(渋滞・雪など)
A
秩父県土整備事務所HP:秩父県土整備事務所管内路面カメラ映像☜をご参考ください。
秩父地域の道路状況がライブカメラでご覧になれます。
※カメラ画像は管理用であり、実際の路面状況と異なる場合があります。当該道路走行される場合には、実際の路面状況、交通規制等に従い安全に走行してください。
Q5.お寺の近くまではバスを使いたいです
A
※バスの運行本数が少ないので事前に調べておくことをおすすめします。
秩父札所バスルートマップ☜をご覧ください。
Q6.宿泊情報を知りたい
A
宿ネットちちぶ☜をご覧ください。
お電話の場合は、秩父旅館業 協同組合までお問合せください。
TEL:0494-24-7538
Q7.札所27番大渕寺に関する注意点
A
秩父札所27番大渕寺に関するお問合せ・ご意見を多数いただいております。
当会といたしましても長年改善を促しておりますが、芳しくない現状にあります。
ご参拝・ご来訪されます方は、以下の内容にご留意の上、お参りをなさってください。
【札所27番の御朱印について】
札所27番においては「御朱印は観音堂で参拝をした証である」という御朱印本来の意味を厳格に実践しております。
その為、御朱印をうける際には①②の順守をお願いいたします。
①観音堂(月影堂)で参拝をする。
※山門に入って正面にある階段の上、山の中腹にあるお堂が観音堂です
※山門を入ってすぐにある建物は、観音堂ではありません
②参拝が終わったら、納経所(御朱印所)で御朱印をうける。
※参拝の作法につきましては【参拝の心得 基本編】☜をご参照ください
【札所28番の冬季閉鎖と御朱印について】
札所28番は冬季期間(12月〜2月末)は閉鎖となります。
冬季期間は、札所27番において札所28番の御朱印もあわせて授与いたします。
その為、2ヶ寺分(27.28番)の御朱印料を27番にてお納めください。
【札所27番の駐車場利用について】
札所巡り、お檀家の方以外(ハイキングや鉄道撮影など)での駐車場利用はお断りしております。
目的外の長時間における駐車場のご利用はご遠慮ください。
【お問い合わせ先について】
本件に関しまして、引続き当会で協議をして参ります。
上記内容に関連したご質問やご意見等がありましたら、秩父札所連合事務局までご連絡をお願いいたします。
・TEL:0494-25-1170(平日10-15時)
・FAX:0494-25-1268
・Mail:chichibukannon@gmail.com
・【お問い合わせフォーム】☜
皆様がより良い巡礼・観光ができますことを心より願っております。
秩父札所連合会 合掌
【その他】
Q1.秩父札所巡りをするオススメの時期を教えてください
A
秩父札所巡りは通年を通してお楽しみいただけます。
3月上旬~4月下旬は梅・桜といった春の開花があり、
10月下旬~12月上旬はモミジなど落葉樹の紅葉があります。
8月頃の真夏は熱中症にお気を付けいただき、1〜3月頃は降雪にお気を付けください。
真夏と真冬は参拝者は多くないので、スムーズな巡礼が可能です。
5月GWの秩父芝桜と、12月2/3日の秩父夜祭の際は、多くの観光客の来訪がある為渋滞が発生しやすい時期です。
横瀬町や秩父市街地を避けて(特に1〜18番)、お参りすることをお勧めします。
また秩父地域は8月がお盆の為、札所寺院でお檀家さん向けの法要(御施食)が行われている場合があります。
その際は駐車場の混雑や、御朱印を受けるまでに時間がかかる可能性があります。
Q2.難所はありますか?
A
●31番観音院
車の方にとっても難所となります。
駐車場から観音堂まで、約300段の階段があります。
―――以下、徒歩での難所―――
●1番四萬部寺から2番真福寺への巡礼道
急な登り坂です。舗装されている道を1時間ほど歩きます。適度に休憩をとりながら登りましょう。
※秩父札所の中で三番目に大変な難所です。
※本来の巡礼道とは異なりますが、足腰に自信のない方は直接光明寺(札所2番納経所)にてご参拝いただくことも選択肢です。
●22番童子堂から山道に入り25番久昌寺まで続く巡礼道
「江戸巡礼古道長尾根道」と呼ばれてます。
景観も雰囲気も良く、山道が多く、これこそ「古道」といった巡礼道です。
●30番法雲寺から31番観音院へ至る巡礼道
距離が長く、沢を渡り山を越える巡礼道で、難しい巡礼道の一つです。
複数の巡礼道がありますが、荒川西小学校付近を通り、道の駅「両神温泉薬師の湯」を通るルートがオススメです。
●31番観音院から32番法性寺へ至る「大日峠」(舗装された迂回路もある)
小鹿野警察署付近から山道を1時間半ほど歩きます。沢を数回渡りますが、古の巡礼道の雰囲気を残す道です。
※秩父札所の中で二番目に大変な難所です。
古洞峠:三島バス停付近から津谷木橋を渡り、右手に入る舗装道路
●33番菊水寺(道の駅龍勢会館)から34番水潜寺へ至る「札立峠」(舗装された迂回もある)
山道を2時間ほど歩きます。
杖の用意をオススメします。※秩父札所の中で一番大変な難所です。
Q3.秩父は雪が降りますか?
A
雪はそれほど多くは降りません。
①12月に雪が降ることはほとんどなく、1月下旬から3月上旬に降ることが多いです。
②降る回数は東京と同じくらいで、降る量は東京の約2-3倍です。
③舗装道路は除雪され早く解けますが、山中は雪が残りやすいです。
東京が雪の際は、秩父でも降っている可能性が特に高いです。
※雪の時は御朱印所が閉鎖される場合もあります。
その際は当HPにて可能な限り情報発信をいたします。
Q4.秩父札所の御朱印は何が書かれていますか?
A
秩父札所御朱印の解説☜をご参考ください。
※必ずしもこの限りではない場合もあります。
Q5.納札(おさめふだ)とはなんですか?
A
納札(おさめふだ)は、参拝の証(記念)として名前と願い事を記入し、「納札入れ(銀色の箱)」に納めます。
秩父札所巡りをする際には、納札があったほうがより巡礼らしさを楽しめます。
古くは千社札とも呼ばれ建物(伽藍)に直接は貼り付けていましたが、
現在は建物の劣化防止等の観点から、貼らずに納める形となりました。
Q6.札所27番大渕寺を参拝の関する際の注意点
A
秩父札所27番大渕寺に関するお問合せ・ご意見を多数いただいております。
当会といたしましても長年改善を促しておりますが、芳しくない現状にあります。
ご参拝・ご来訪されます方は、以下の内容にご留意の上、お参りをなさってください。
【札所27番の御朱印について】
札所27番においては「御朱印は観音堂で参拝をした証である」という御朱印本来の意味を厳格に実践しております。
その為、御朱印をうける際には①②の順守をお願いいたします。
①観音堂(月影堂)で参拝をする。
※山門に入って正面にある階段の上、山の中腹にあるお堂が観音堂です
※山門を入ってすぐにある建物(左側)は、観音堂ではありません
②参拝が終わったら、納経所(御朱印所)で御朱印をうける。
※参拝の作法につきましては【参拝の心得 基本編】☜をご参照ください
【札所28番の冬季閉鎖と御朱印について】
札所28番は冬季期間(12月〜2月末)は閉鎖となります。
冬季期間は、札所27番において札所28番の御朱印もあわせて授与いたします。
その為、2ヶ寺分(27.28番)の御朱印料を27番にてお納めください。
【札所27番の駐車場利用について】
札所巡り、お檀家の方以外(ハイキングや鉄道撮影など)での駐車場利用はお断りしております。
目的外の長時間における駐車場のご利用はご遠慮ください。
【お問い合わせ先について】
本件に関しまして、引続き当会で協議をして参ります。
上記内容に関連したご質問やご意見等がありましたら、秩父札所連合事務局までご連絡をお願いいたします。
・TEL:0494-25-1170(平日10-15時)
・FAX:0494-25-1268
・Mail:chichibukannon@gmail.com
・【お問い合わせフォーム】☜
皆様がより良い巡礼・観光ができますことを心より願っております。
秩父札所連合会 合掌
【用語解説など】(準備中)
Q2.納経と御朱印について
『納経』とは「お経(読経/写経)を納める」ことで、
『御朱印』とは「参拝した証に朱印を押す」ことです。
そこから転じて、御朱印を受けることを
秩父札所では、『納経』と『御朱印』はほぼ同じ意味で使われています。
現在では、観音様に手を合わせていただくだけでも、参拝した証である「御朱印」を授与いたします。
秩父札所では34ヶ所それぞれの御朱印が受けられます。
Q3.重ね印と重ね始めについて
通常の御朱印は、まっさらな納経帳に「朱印」と「書入れ」をいたします。
重ね印(かさねいん)は、2巡目から上記の同じ納経帳に「朱印」のみをいたします。
札所巡りを2巡・3巡・4巡・5巡・・・と続けていくと、納経帳の各頁が朱印で真っ赤に染まっていき、より綺麗な納経帳になります。
秩父札所ではこの「重ね印」が盛んであり、巡数と朱印と年月を重ねることでより秩父札所を満喫していただくとともに、
より功徳を積むことができると言われています。
2巡目を始めることを「重ね始め」と呼びます。
1巡目を満願された後に、時期の良い頃に秩父札所巡りの2巡目を始めていただけると幸いです。
Q4.笈摺と白衣について
笈摺(おいずる)と白衣(びゃくえ)は巡礼中に身につける白い装束のことです。
笈摺と白衣に明確な違いはありませんが、主に袖がない方を笈摺と呼びます。
秩父札所では公式の巡礼用品として袖がない笈摺☜(公式通販)を取り扱っております。
この巡礼装束である笈摺は「晴れ着」といった表現を用いて、正装といった表現はいたしません。
着用に資格などは不要で、どなたでも自由に着用ができます。
本格的な装束「晴れ着」で巡礼をされたい方はご着用ください。
Q5.お姿と御影について
『お姿(すがた)』と『御影(みえい/おみえ/みかげ)』は同じものを指します。
秩父札所では『お姿』と言われることが多く、各寺院のご本尊である観音さまが描かれています。
お姿は観音さまの分身であり、自宅にお祀りすることで、日々親しく参拝することが出来ます。
白(白色の紙に黒字):200円
紺(紺色の紙に金字):300円
納経帳とは別に「お姿入れ」などで保管・管理をするのが一般的です。
お姿入れは秩父札所1番四萬部寺でお求めいただけます。
Q6.先達とサイクル先達について
公認先達とサイクル先達はどちらも秩父札所連合会が主幹となりますが、内容は別のものになります。
秩父札所公認先達☜は、巡礼文化の普及が目的であり、納経に関する規定や研修会開催なども行われています。
秩父札所サイクル先達☜はサイクリングが主体であり、いわゆる巡礼の体験・第一歩としての位置づけとなります。
詳細は各専用ページをご覧ください。
Q7.お賽銭とおつりについて
お賽銭の金額に決まりはありません。
また金額や硬貨の種類によるご利益や、縁起の良し悪しも一切ございません。
納経料は通常500円(重ね印200円)です。
秩父札所34ヶ所分の硬貨をご用意する必要はありません。
お札であったとしても、おつりとしてお返しいたします。
Q8.お賽銭と燈明・線香ついて
お賽銭は、観音さまへの感謝や願いをお伝えする際に納める財物です。
財物とは「自身にとって価値がある大切なもの」のことです。
現在では硬貨(現金)が一般的ですが、
昔からお米・野菜・菓子・酒などの食べ物も財物として供え(納め)られてきました。
燈明(とうみょう)はロウソクのことで灯りを示し、線香の煙は香りを示します。
お賽銭・燈明・線香は、いずれも自身の浄化(お清め)や、観音様を楽しませる(感謝する)といった意味合いもあります。
Q9.満願と結願について
準備中